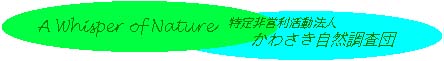
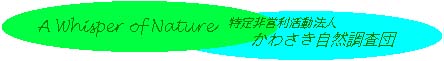
|
ハンノキ林の水辺再生 日 時)10月28日(火) 9:00〜12:00 晴 場 所)生田緑地 ハンノキ林(A07-03)、湿地地区、上の田圃地区 活動者)岩田臣生 今夏は谷戸の水涸れが酷くて、水辺の再生活動をしなければならないと思い、 今までは、できるだけ手を入れないようにしていた場所に、 思い切った大改造?をするつもりで、ハンノキ林東地区の斜面下の草地に数個の穴を掘って、水の染み出す様子を観察してきました。 生田緑地の湧水は、広い範囲からの地下水が湧き出ているものではなく、生田緑地の基底部の地層である飯室層の上の押沼砂礫層の上の関東ローム層に貯留された雨水が 下層に染み出して、不透水層である飯室層の表面で周囲に染み出してくるものです。 このため、ある程度の合流があってからでないと水流は生まれません。 この1〜2ヶ月の活動に基づいて、源頭部に、谷戸の水源池と呼べるような大きな水溜まりをつくるのも面白いと考えるようになりました。 これは、今夏のような渇水が起こった時には、谷戸の溜め池としての機能も果たせるかも知れません。 掘ってきた水溜まり穴が集まる、やや平坦な、この場所に、1つの大きな水面をつくろうと思ったのです。 ここは、ハンノキ林を隔てて、木道から少し離れていますので、大型の野鳥が利用できるような水場にもなりそうです。 冷たい湧水ですが、トンボなどの昆虫などにも歓迎してもらえるような気がします。 この日は、その水源池づくりは行わずに、そこから下流?の階段をつくる活動を行いました 

下流部の作業の途中で、ここに戻って、休憩していたら、マユタテアカネが水面を飛び、オオアオイトトンボが水辺の草に止まっていました。 
キチジョウソウが咲いていました。 
この平坦な場所から先は、少しずつ傾斜が強くなっていますので、傾斜に合わせて、階段状に連続する水溜まりをつくる穴掘りを行いました。 掘った土の色が変わると、水が染み出してきました。 水が土の中に染みて、ゆっくり流れているのだと感じました。 







ハンノキ林中央部を横断する木道の所まで来て、木道に上がり、振り返りました。 昔の記憶では、もっと水面がある湿地が続いていたように思いました。 
木道を越えて、東支谷戸に入ってみましたが、過去に掘った水溜まり穴の水が消えていました。 しかし、最奥部には、水が見えていました。 この支谷戸でも、数ヶ所に水溜まり穴を掘って、地下の水の状態を調べてみる必要がありそうです。 ハンノキ林を出て、湿地地区に移動し、水の状態を調べました。 様々な草が繁茂していましたが、ミゾソバの開花は、盛期を過ぎたようでした。 湿地地区上側の木道を歩いていたら、シロヨメナが開花盛期になっていました。 木道から届く範囲ですが、大きなアズマネザサを刈りました。 
上の田圃地区の状態も見に行きました。 下の段は、まだ湛水していませんでしたが、畦沿いに掘った溝には、水面が広がっていました。 谷戸の湧水の流量は、少し増えたようです。 

木道の手摺には、マユタテアカネが休んでいました。 

(上図)10/28(火)の活動範囲図 |
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動