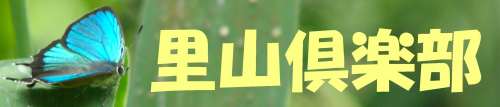
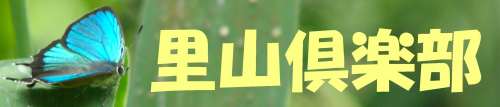
|
ú@2008N119ú(y)10:00`12:40@ÜAĶĒ W@köąQKïcšAGčXVnæ(A06) ut@ĄÔûXq QÁ@iķcÎnAķĮĶcïï·jq{é @@@iķcÎnĖGØŅðįÄéïjāVõã @@@iĐíģŦĐRēļcAĻĮjēĄoėqAgc―ü}AgŊq @@@iĐíģŦĐRēļc crIg[vĮjãÆÍqAŽōbCAqģl @@@iĒRĖĐRwZjāĄéARāáARāt @@@iköąjx]mAéØCiARûŨŊ @@@isŊïąĮjâcbķAâcFü @@@@@@@@@@@@@@@@@@QÁŌPVl ķcÎnGčXVnæ(A06)ÍARiŅi1,200―û[gjð1998NÉF°ĩ―næÅ·B ĄÔûXqmÍAąĖÉ600―û[gĖēļæðÝčĩAN4Đį4NÔÍAŧĖãÍN4ņĖj^OðAĐíģŦĐRēļcAĻĮĖĶÍðūÄĀ{ĩÄŦÜĩ―B ĄņÍAąĖ8NÔÉí―éj^OĖĘðÜÆßįęÄAĄãĖYnæ(A06)ĖAķĮðlĶé―ßĖMdČf[^ð\ĩÄšģĒÜĩ―B ķcÎnĖũŅÍSĖIÉVîŧŠiņÅĒéąÆÍmĐÅA·úIXpÉĻĒÄĩļÂSĖĖXVŠißįęéæĪÉĩÄĒąÆŠA ķcÎnÉĻŊéķĻ―lŦÛSÆĒĪ_ĐįādvČÛčÆČÁÄĒÜ·B ąĖ_ĐįĐéÆAY][ĖÂÓĄÍåŦAŧĖÚWAķÆĄãĖĮ{ôðßÄĒbĩĒÉA vĒŠŊļAŽwUNķŠ2lASNķŠ1lQÁĩÄę―ąÆÍf°įĩĒąÆÆvĒÜ·B ―ŋĖŪÍyĩ éąÆŠî{Å·B 






æķĐįĖĻbÆŋ^ĖãAGčXVn(`OU)ÉFÅsŦAũŅĖÉgðuĒÄAĄxÍĖSĖÅũŅĖlqðīķæčAąņČũŅÉČÁ―įĒĒČÆĒĪC[WðcįÜđÄĒŦÜĩ―B F°ÆÍĒĒČŠį°ĖđļÉcģę―žaQOðīĶéũØā―{ĐĐóŊįęÜĩ―B°ĖÆŊÉâAģę―ÆĒĪũØĖĪŋPĖÄAĶįę―āĖÍžaW`POÉŽ·ĩAĖsíęÄĒ―æĪČdYpĖ―ßĖ°ĖÉÍKúÉČÁÄĒÜĩ―BR{AĶÅâAģę―āĖÍŽ·ŠŦAÍęÄĒéāĖŠ―ĐįęÜĩ―BGčXVðÚ_ņÅ°Ėģę―RiÍ{ĖGčð§ŋã°―ÆąëÅÍęÄĒÜĩ―B šāÅĖæķĖĻbÉ Á―æĪÉtwŠúAqĮā―ŋĖēŨÅÍÅåPVA―ÏÅPQÅĩ―BąĖtwĖ―ßĐA2006NĖēļÅÍ{AĻŠUOíA2007NĖēļÅÍSPíÉļĩ čAíLxŦŠášĩÄĒÜ·B 











ĶĒúÅĩ―ĖÅAköąÉßčAÚWAķÆąęĐįĖAķĮĖißûÉÂĒÄbĩĒÜĩ―B ŧĖĘAGčXVnÆĩÄĖĘuÃŊðpģĩAĮģę―GØŅÆĩÄÏ@ïÉpÅŦéūéĒGØŅÉ·éąÆÆČčÜĩ―B ũØ°ĖĖAķĮÍNxĀ{Æ·éąÆAïĖIČ°Ėû@ĖÚŨÉÂĒÄÍąĮŠvæ·éąÆÆČčÜĩ―B Ü―ĄNxĖ[uÆĩÄÍAų čÆtĐŦðĀ{·éąÆÆAúöēŪÍąĮÉCđÄāįĪąÆÆĩÜĩ―B 


sŊïĖŪÅāAĖrĖOķĻėėíÍAĒRĖĐRwZĖqĮāÉāQÁĩÄāįĒ―ĒÆvĒÜĩ―ŠAÚWAķðlĶéæĪČvOÉÍQÁ·éqĮāÍĒČĒāĖÆčÉßÄĒÜĩ―BÅ·ĐįAËRAĩxęéÆĖdbðāįÁ―ÍÁŦÜĩ―BĪęĩĒTvCYÅĩ―B qĮā―ŋŠAålÆęÉĐRðÛS·éŪÉQÁ·éæĪÉČéąÆÍĒRĖĐRwZĖÚIÉā éąÆÅ Á―ÆãĐįCÃĐģęÜĩ―B ŪĻūĐįÎÛÉČÁÄũŅÅÍÎÛOÆčÉßÄĒ―ĖÍëčūÆCÃĐģęÜĩ―B ÅāAąęĐįÍOÉ\ĩņÅšģĒBæëĩĻčĒĩÜ·B sŊïIđãAâcÍAĒRĖĐRwZĖqĮā―ŋĖĻŲÉÂŦ ĒAJËÉ~čÜĩ―B cņÚÉÍXŠÍÁÄĒÄAqĮā―ŋÍēÉČÁÄĩÜĒÜĩ―B qĮā―ŋŠgßČęÅVRĖXÉoïĪ@ïČĮÍāĪģČč éĖÅĩåĪB ÁĒ―ĖÍAXĖšÉĖ·UöĖ ķbŠĒÄAQÄÄęÉūņūtĖšÉBęÜĩ―B 
















|
 ĐíģŦĐRēļcĖŪĖy[WÖ
ĐíģŦĐRēļcĖŪĖy[WÖ