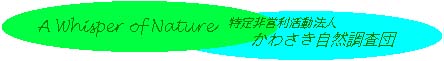
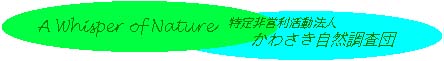
|
谷戸の水辺保全 日 時)2025年 8月14日(木) 9:00〜12:00 曇後晴 場 所)生田緑地 湿地地区、上の田圃地区、下の田圃地区、城山下谷戸合流部、その他 活動者)岩田臣生、伊澤高行 水不足の夏は、水辺保全活動が大変です。 湿地地区(B05)、上の田圃地区(B06)、下の田圃地区(B07)などは、私たちが、根本的に状態を変えて、創りだした水辺ですから、 それなりの責任を持って、保全活動に取り組まなければならないと考えています。 下の田圃地区については、湧水が入る田圃の跡地ということで、生きもののための田圃づくりを目指した私たちにとっては、保全すべき重要な水辺です。 田圃の水辺には、ケラ、ヤマトクロスジヘビトンボ(幼虫)、クロセンブリ(幼虫)、カワニナなどが棲息し、田圃裏の水流には、オニヤンマ(ヤゴ)が棲息し、 両方の水域を使って、ホトケドジョウが棲息しています。 田圃づくりは、厚く絡み合ったチゴザサやヨシの根を取り出すことでしたが、 その絡み合った根の中には、ミカドガガンボ(幼虫、後半は蛹)が多数いたので保護しました。 田圃づくりの最中は、シマヘビ、シオヤトンボ、シュレーゲルアオガエル、オオスズメバチなどが、毎日、顔を出してくれました。 植物は、ミゾハコベか、ミズハコベと思われる水草、コナギ、 タガラシ、イボクサ、 タネツケバナ、セリ、ヒメシダ、コガマ、ミゾソバなど、 水田耕作をしていた時は、草取りの対象であったであろう田圃雑草が多く見られました。 生田緑地の谷戸の水辺に復活させて、保全してきた絶滅危惧植物は、その育ち方を見ていると、 田圃の土と湧水と日照という条件を環境条件とする植物であることが良く分かります。 今年は、下の田圃には、稲を植えないで、生きものに解放しましたが、コナギなどの田圃雑草にとっても、 好みの環境となったのでしょう、著しく繁茂してきたので、 先週の木曜日、8/7(木)に、チョウジタデ、コナギ、 クワイなどの草刈りを行いました。 しかし、一昨日、8/12(火)に、状態を観察したら、草むしりはまだ足りないと感じましたので、この日もウェイダーを履いて、田圃に入りました。 私たちが活動している生田緑地の谷戸の水辺は脆弱なものですから、大勢で一緒に活動することは困難です。 一人一人が、自分の能力に応じて、取り返しのつく範囲の活動を行う方法が良いと考えています。 今回は、伊澤さんが参加して、ハンノキ林上の池の泥上げをすると言い出しましたので、水涸れし易い場所の点検補修をしてから、 余裕があったら行ってもらうことにしました。 そこで、湿地地区(B05)は伊澤さんに任せておいて、下の田圃に向かう途中、上の田圃の水の状態を観察することから始めました。 (上の田圃地区) 導水路には、少ないながらも、水が流れていました。 田圃の上の段は湛水し、下の段に落ちた水が、畦沿いの溝の一部、木道側と芝生広場側の途中で止まっていました。 8/9(土)、8/10(日)の雨は谷戸の水辺を潤して、8/12(火)の上の田圃は、水面が全体に広がっていたのですが、この日は、早くも、土嚢堰側の溝が水涸れを起こしていました。 そこで、下の段の溝を歩いて、水面を踏みつけ、水が抜けていそうな柔らかくなった部分を見つけて、そこの水漏れを止めることを試みました。 そうしておいてから、下の田圃に向かいました。 




(下の田圃地区) 下の田圃に着いてから、ウェイダーに履き替えました。 9:26 WBGT 23.5℃、周囲温度 27.9℃、湿度 60.7% 今回は、立鎌を持って来て、これを杖替わりにしたり、鎌として、少し離れた場所のコナギをむしったり、前回に比べて、格段に楽になりました。 気になった絶滅危惧種に接していたコナギは、殆んど、取り除きました。 ヨシの茂みに近い所も、手を入れた方が良いとは思いましたが、晴れて、日が当たるようになったら、急に暑くなってきましたので、この辺で止めておくことにしました。 助けた絶滅危惧種が種子を実らせてくれれば、確実に、命を繋ぐことができます。 


コナギは、開花し始めていました。 生田緑地のコナギの記録は、川崎市北部の植生−生田緑地・稚児の松(鈴木正,1967)の記録以降、 第6次川崎市自然環境調査報告書(吉田多美枝他植物班,2007年)に記録されるまで記録がありませんでしたが、 このコナギの記録が、私たちが再生した下の田圃のコナギでした。 コナギ(調査団ホームページ) 
下の田圃は、小さいのですが、水面が広がったせいか、シオカラトンボとオオシオカラトンボが6〜7匹で群れていました。 通りかかった捕虫網を持った父子が、「ここは、めっちゃ、トンボがいるよ!」と大声で騒いでいました。 
まだ、11時でしたが、木道に上がって、長靴に履き替えました。 上の田圃に来たら、伊澤さんが、田圃周りの穴を埋める作業をしてくれていました。 私が、朝行ったことの効果は全く無く、水面は広がっていませんでした。 

11:30 WBGT 27.2℃、周囲温度 29.1℃、湿度 72.4% 伊澤さんが止める様子が無いので、湿地地区に移動して、状態確認をしました。 水漏れを補修したと聞いていましたが、水涸れしたことが分かる状態でした。 このように短期間に水涸れを繰り返すようでは、暑いからといって、休んでもいられません。 
|
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動