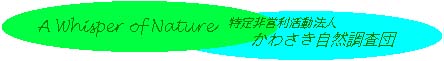
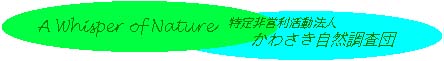
|
自然探勝路のアズマネザサ刈りと谷戸の水辺保全 日 時)8月19日(火) 9:00~12:00 晴 場 所)生田緑地 ハンノキ林源頭部自然探勝路、湿地地区、上の田圃地区、下の田圃地区 活動者)岩田臣生 前回、8/14(木)の活動終了後に、生田緑地の指定管理者である生田緑地共同事業体の髙木さんから相談がありました。 来園者から、ハンノキ林源頭部の園路の草刈りをして欲しいという要望があったが、どうしようかということでした。 何が生えていても気にせずに、通行可能幅員を広げるために、全てを刈ってしまってよいかということだと思いましたので、 現状を調べて、植物観察の対象になりそうなものには名札をつけるなど、単に通行するためだけではなく、自然観察に配慮した管理をしたいと答えました。 生田緑地はチョウなどの昆虫の吸蜜源が少ないので、もし、開花中の植物があるようなら、必要の無い草刈りは止めたいと思いました。 その時は、疲れてもいたし、時間も無かったので、調べにも行けませんでした。 この日は、この課題に対応するために、何の名札を作成すれば良いかを調べる活動を行うことにしました。 対象園路は、下図の赤線部分(2025/8/19と記したところ)です。 現在、萌芽更新地区の上側の園路が通行禁止になっていますので、ハンノキ林の西側の園路を上った時には、この部分を通行することになります。 
ハンノキ林上のデッキの方から、現地を覗いてみると、次の写真のように、人が一人通れるようにはなっていると思いました。 

残念ながら、想像していた状態とは異なり、来園者が問題にしたのは、萌芽更新地区側の斜面に繁茂したアズマネザサのことだろうと理解しました。 この園路は、平坦な部分は狭くて、斜面裾部の緩傾斜の部分も使える状態になっていることが求められていると思います。 そこに、アズマネザサやシダ植物が繁茂し、所々に、幼木も生えていて、それらが、通行の妨げになっているのだと思いました。 ミヤマナルコユリが黒い実をつけていたりしましたが、期待していたような開花中の草本は、殆ど見当たりませんでした。 実際に、アズマネザサなどを刈りながら、地形と植物を観察することにしました。 名札をつけて管理したいものは少ないと思いました。 まず、キンミズヒキ?かと思われる葉が、アズマネザサの茂みの中から出ていましたので、周囲のアズマネザサは刈りました。 
ハナイカダ?と思われる幼木が数本ありました。 絡みついていたヘクソカズラが蕾をつけていましたが、近くの陽当たりの良い場所では咲き始めていましたので、ここで絡みついていたツルは外させてもらいました。 


ここに続く木道の手摺は、このような設えの部分があります。 ここは腰かけることが可能なので、素晴らしい仕掛けだと思います。 上の田圃地区は木陰のベンチが無くなったので、手軽な木陰の休憩場所がありません。 木道の木蔭になっている場所の手摺の一部に、このような仕掛けがあると、田圃辺りで活動をしている者にとっては、非常に助かります。 壊れた手摺の改修を、このように行っていただけると有難いと思いました。 
問題の園路に入る所の両側の樹木の枝を落としたり、除伐したりして、通り易くもしました。 
10:00 WBGT 23.1℃、周囲温度 26.6℃、湿度 77.0% 更に、斜面裾部のアズマネザサ、シダ植物などを刈っていきました。 
途中に、オトコエシが大きく育って、通行を妨げていました。 近くのアズマネザサを伐って、邪魔にならないように、支えにしましたが、この支柱は一時的なものです。やり直した方が良いと思います。 間もなく開花して、貴重な吸蜜源になります。 来園者に折られないように、支柱と名札が必要と思いました。 

調査のためのアズマネザサ刈りを終えました。 刈った材の片付け、名札付け、支柱立てなど、丁寧な仕上げ作業を行えば、課題は解決できます。 



クロアゲハが1頭、辺りを調べるように、飛んでいました。 10:58 WBGT 26.1℃、周囲温度 28.7℃、湿度 74.1% 尾根路を使って、湿地地区に移動しました。 ハンノキ林東地区に発芽したコナラは順調に育っています。 
湿地地区は、入って直ぐのサワガニ穴をアライグマが漁ったのか、大きな穴が並んでいて、その一つに、水が吸い込まれて、消えていました。 これらの穴は踏み潰して、水漏れを止めましたが、流量は非常に少ないままです。 絶滅危惧種の水辺は完全に涸れました。 
3段目に落ちる水も消えていました。 竹林下からの水を調べようとしたら、4~5羽のコジュケイの母子を驚かせてしまいました。 コジュケイの母子は水路沿いを逃げました。 
上の田圃地区に移動しました。 導水路の水は涸れてはいませんでしたが、非常に少ない状態でした。 田圃は、下の段は水涸れ、泥上げを行った溝には水面がありました。 
下の田圃の状態も見に行きました。 まだ水は涸れていませんでしたが、こちらも涸れかけているように見えました。 
|
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動