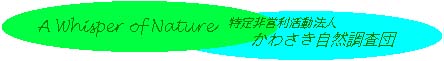
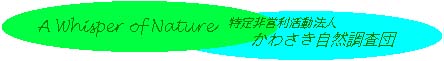
|
谷戸の生物多様性保全 日 時)8月7日(火) 9:00〜11:30 曇、一時小雨 場 所)生田緑地 下の田圃、谷戸の水辺 活動者)岩田臣生、田村成美、伊澤高行 一昨日、8/5(火)は、谷戸の水辺から水が涸れた状態を観察して、この状態に対して可能な手入れを考えて、 それだけを行いました。 後は、雨が降って、水流が息を吹き返してからのことだと思っていたので、この日は、下の田圃の絶滅危惧種の保護のための草むしりを行うつもりでいました。 すると、生田緑地では、少しは雨が降ったそうで、若しかすると、面白い場所があるかも知れません。 作業的活動を迫られていないのですから、皆には、谷戸の水辺をじっくり観察して、これから何をすれば良いかを考えてもらうことにしました。 そして、私は、今年の冬から春にかけて、消えてしまったかも知れないと心配し、バタバタと慌てることになった絶滅危惧種の保護活動を楽しませてもらうことにしました。 水田ビオトープ班の活動は、2004年に、下の田圃を再生することから始めたのですが、 同年、本格的に、生田緑地の自然を保全する活動を始ることを考えて、シンポジウムを開催し、 状態をよく観察して、理解して、考えて、取り返しのつく範囲で活動して、その結果を観察して考えることを繰り返しています。 本格的に始めた最初の自然保全活動が、この絶滅危惧植物を復活させるための湿地再生でした。 この活動は成功して、当該植物は復活したので、その植物の保護管理を続けています。 神奈川県RDでは絶滅危惧IA類とされた植物なのですが、各地から消えて、今では、県内分布は生田緑地だけになってしまったようです。 水田ビオトープ班として保護管理していると言っても、基本は生物多様性保全なので、この植物だけを考えての活動は、殆どしていません。 この植物が消えることが無いように、田圃の土と湧水と日照という環境を考えた場所を保全しておくことで考えています。 ただ、今年は、少し意識して、保護しているつもりです。 前回、下の田圃に入ったのは、6/24(火)で、発芽したチョウジタデやコナギを除草する活動を行いましたが、 それらが息を吹き返して育ち、保護すべき植物を覆うように繁茂してきましたので、この植物の周りの草むしりをすることにしました。 
下の田圃までは雑のう袋に入れて運んできたウェイダーに、木道の上で履き替えてから、40〜50cmに育っていたオオミゾソバを掻き分けて、田圃に入りました。 流石に、下の田圃に入っている水も、今回は流量が少なくなっていました。 田圃には、オオシオカラトンボ(オス)がヨシに止まって、縄張りを監視していました。 
下の田圃は深い湿田なので、太腿まで泥の中に沈めて、倒れないようにバランスを取りながら、少しずつ前進しなければなりません。 進もうとしたところで、やっと、目の前に、大きなクモがいることに気がつきました。 ナガコガネグモです。 かつては、田圃のクモと呼ばれていたこともあるクモでしたので、上の田圃から消えた時は、残念に思いました。 谷戸の生物多様性にとっては、いるべき生物の一つだと思っているので、嬉しい出会いでした。 
今回は、手の届く範囲の辺りの草を刈ったり、むしったりして、それを土の中にに押し込むようにして、その上に乗って進むようにして、少しずつ移動しました。 保護対象の植物は、既に、沢山の細い花茎を伸ばして、先端に緑色の種子をつけているものも、多数ありました。 その花茎は細いのですが、枝分かれしていて、大きく横に細い伸びた枝は水面に着いていたりするので、 手の届く所に生えていたヨシを取って、それを支柱にして、この細い枝を支えてあげながら進みました。 この時の動きは木道から見ていると不思議な動きだったようで、それを観察していたメンバーから、何をしていたのかと尋ねられました。 このような観察は大事なことだと思いますので、嬉しい質問でした。 畦からは、ミゾソバが茎を伸ばしていましたし、田圃の中は、コナギや、チョウジタデや、クワイなどが繁茂していたので、それらが草むしりの対象でした。 草むしりを行って、地面が見えるようになったら、そこには、地中から空中に伸びようとする白い根が無数に生えていました。 チョウジタデが気根を出していたのです。 コナギなどの密集している下には、小さなヤゴが歩いていました。 ヨシの茂みに近い辺りは、適度に、上空が開けていて、浅い水中に、カワニナがいました。 




保護すべき植物が生えていない辺りでは、泥の上にコナギやチョウジタデを積んで、その上を這うように進む活動になりましたが、 泥の中から足を抜くのは容易ではなく、手で足を掴んで、引き上げる必要がありました。 そのような恰好で周囲を見渡したら、近くのチョウジタデの密集する中に、ツマグロヒョウモンが来ていました。 
ナガコガネグモに出会えて、ヤゴやカワニナも観察できて、絶滅危惧種がチョウジタデなどの草に覆われている状態を脱して、木道から観察できるようになったので、 真夏の活動としては、この程度で良いことにさせてもらいました。 


この日の活動を終えることにして、木道に上がって、ウェイダーを脱ぎました。 11:30 WBGT 24.3℃、周囲温度 28.1℃、湿度 63.7% 帰り道の萌芽更新地区下の園路には、サツマノミダマシがいました。 
|
 かわさき自然調査団の活動
かわさき自然調査団の活動